|
|
|
水端
mizuhana

みづはな【水端】
物事の最初。出はじめ。はじまり。
「忘れられた古の奈良に伝わる技術を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する」
油長酒造の新たな取り組みです。
【水端の3つのルール】
○大甕仕込み
室町時代の寺院醸造で用いられた3石の大甕を再現
信楽焼の窯元で大甕を焼成
○水端専用蔵享保蔵で醸す
初代、山本長兵衛秀元が精油業から醸造業を創業した際に享保年間(1700年代頭)に建造した酒蔵。
2階部分をリノベーションし、享保蔵で100年ぶりに酒造り。
享保蔵では酒造りすべての工程を享保蔵のみで完結します。
風の森醸造とは完全に切り離した独立した酒蔵です。
○奈良に伝わる古典醸造法を参考
平城京出土の木簡(国立醸造所/造酒司)
御酒之日記(寺院醸造)
興福寺多聞院日記(寺院醸造)
水端ではその全てを室町時代の仕込み容器、大甕で仕込むことをルールにしています。
この大甕は酒蔵に残る備前の大甕(約300L)を現在の信楽焼で再現焼成したものです。
1回の仕込みで100kgのお米を用いて、約300本(4合瓶換算)の清酒を造ることが出来ます。
卵形の形状は液体の対流性が高く、もろみの発酵が促進される傾向があります。
また、土器に含まれるミネラルがもろみ中に微量に溶け込むことで発酵が旺盛になる傾向があります。
そのため、発酵初期の温度上昇が高く、豊富な有機酸を生み出すことにも繋がっています。
また、保温性はステンレスタンクより高く、木桶よりは低い特性があり
冷却機能を持たない容器ではありますが、四季を通じて非常に温度管理しやすい一面があります。
甕で仕込んだお酒の魅力をより伝えるため、瓶ではなく陶器の容器を使用します。
伝統と歴史を併せ持つ美濃焼による水端専用の陶器となっています。

油長酒造
水端 1355 2023
|
 |
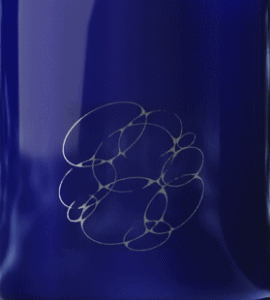 |
甕仕込による古来の製法を再現!
油長酒造の新たな取り組みとなる「水端(みずはな)」は、”忘れられた古の奈良に伝わる技術を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する”をテーマに、古典醸造法を参考にし、大甕で醸造するお酒です。
この「水端 1355」は、御酒之日記に記された、菩提山正暦寺の技法を参考にした夏季醸造0段仕込み(もと搾り)。
時は室町時代1355年。
「御酒之日記」という名の醸造書が書かれました。
この書物には、日本清酒発祥の地として知られる、奈良菩提山正暦寺で醸された菩提泉の製法が克明に記載されています。
「水端 1355」ではこれを参考に醸造。
現代日本では完全に忘れ去られた夏季醸造の技術で醸された稀有な日本酒です。
真夏に発酵温度が30度を超える高温条件下で進める醸造法は、江戸時代に日本酒造りが冬季醸造に移行すると姿を消してしまった技術です。
色調は、やや濁りのあるシャンパンゴールド。
香りにはカラメルやワイルドな乳酸系のヨーグルト香、穀物感や複雑味も感じられます。
口当たりには甘みと共に、グレープフルーツなど柑橘系の酸がしっかり。
軽やかさはありつつも、コクのある旨みや乳酸系のヨーグルト感、複雑味のある複層的な味わい。
ワイルドな要素と共にジューシーさも感じられ、意外に飲み心地よさもあり、キレ味の良さも特徴的です。
温度の上昇とともに、甘み旨みの要素が強くなり、強く濃厚な味わいとなっていきます。
※商品のご購入につきましては、蔵元の意向もあり、お一人さま1商品2本までとさせて頂きます。
※2本以上ご希望の場合は、ご相談ください。
※飲食店さまにつきましては通常通りご購入くださいませ。
|
| 原料米 |
秋津穂 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
12度 |
酵母 |
協会7号系 |
|
 |
|
|
|
|
|
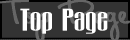 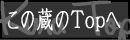 |

油長酒造
水端 1355 2024
|
 |
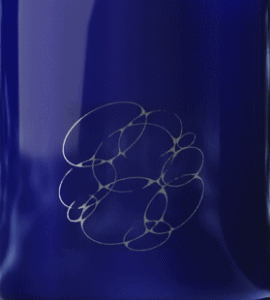 |
甕仕込による古来の製法を再現!
油長酒造の新たな取り組みとなる「水端(みずはな)」は、”忘れられた古の奈良に伝わる技術を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する”をテーマに、古典醸造法を参考にし、大甕で醸造するお酒です。
この「水端 1355」は、御酒之日記に記された、菩提山正暦寺の技法を参考にした夏季醸造0段仕込み(もと搾り)。
時は室町時代1355年。
「御酒之日記」という名の醸造書が書かれました。
この書物には、日本清酒発祥の地として知られる、奈良菩提山正暦寺で醸された菩提泉の製法が克明に記載されています。
「水端 1355」ではこれを参考に醸造。
現代日本では完全に忘れ去られた夏季醸造の技術で醸された稀有な日本酒です。
真夏に発酵温度が30度を超える高温条件下で進める醸造法は、江戸時代に日本酒造りが冬季醸造に移行すると姿を消してしまった技術です。
色調は、綺麗なシャンパンゴールド。
香りには穀物やカラメルなど複雑性が感じられます。
軽やかさを感じさせる口当たりに、しっかりとした濃厚な甘さ。
乳酸系の酸と共に、完熟したリンゴやパイナップル感。
余韻にかけてコクや旨みもあり、香り同様の穀物感やナッツの要素も感じられます。
ややワイルドさや複雑味はありつつも、引けの良さを感じるスマートな仕上がりで、スムーズな飲み心地です。
※商品のご購入につきましては、蔵元の意向もあり、お一人さま1商品2本までとさせて頂きます。
※2本以上ご希望の場合は、ご相談ください。
※飲食店さまにつきましては通常通りご購入くださいませ。
|
| 原料米 |
秋津穂 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
13度 |
酵母 |
協会7号系 |
|
 |
|
|
|
|
|
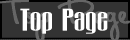 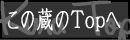 |

油長酒造
水端 1355 2025
|
 |
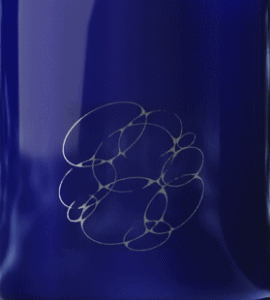 |
甕仕込による古来の製法を再現!
油長酒造の新たな取り組みとなる「水端(みずはな)」は、”忘れられた古の奈良に伝わる技術を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する”をテーマに、古典醸造法を参考にし、大甕で醸造するお酒です。
この「水端 1355」は、御酒之日記に記された、菩提山正暦寺の技法を参考にした夏季醸造0段仕込み(もと搾り)。
時は室町時代1355年。
「御酒之日記」という名の醸造書が書かれました。
この書物には、日本清酒発祥の地として知られる、奈良菩提山正暦寺で醸された菩提泉の製法が克明に記載されています。
「水端 1355」ではこれを参考に醸造。
現代日本では完全に忘れ去られた夏季醸造の技術で醸された稀有な日本酒です。
真夏に発酵温度が30度を超える高温条件下で進める醸造法は、江戸時代に日本酒造りが冬季醸造に移行すると姿を消してしまった技術です。
2024年までは秋津穂を使用していましたが、2025年からは正暦寺産の露葉風を使用。
これにより、古いお寺での酒造りの再現性をさらに高めました。
色調は、綺麗なシャンパンゴールド。
香りには麦茶のような香ばしさ、穀物や乳酸感、カラメルなど複雑性が感じられます。
口当たりには円みがあり、柔らか。
軽やかさのある、しっとりとした飲み口に、甘やかなコクや乳酸系の酸、ヨーグルト感。
梅酒や焼きリンゴのようなニュアンスを伴う甘酸っぱさで、ジューシーな要素も感じられます。
個性的ではありつつも、スムーズさのある不思議な飲み心地良さが楽します。
※商品のご購入につきましては、蔵元の意向もあり、お一人さま1商品2本までとさせて頂きます。
※2本以上ご希望の場合は、ご相談ください。
※飲食店さまにつきましては通常通りご購入くださいませ。
|
| 原料米 |
露葉風 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
12度 |
酵母 |
協会7号系 |
|
 |
|
|
|
|
|
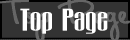 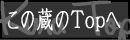 |

油長酒造
水端1355×菩提山正暦寺 2023
|
 |
 |
甕仕込による古来の製法を再現!
油長酒造の新たな取り組みとなる「水端(みずはな)」は、”忘れられた古の奈良に伝わる技術を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する”をテーマに、古典醸造法を参考にし、大甕で醸造するお酒です。
この「水端 1355」は、御酒之日記に記された、菩提山正暦寺の技法を参考にした夏季醸造0段仕込み(もと搾り)。
時は室町時代1355年。
「御酒之日記」という名の醸造書が書かれました。
この書物には、日本清酒発祥の地として知られる、奈良菩提山正暦寺で醸された菩提泉の製法が克明に記載されています。
「水端 1355」ではこれを参考に醸造。
現代日本では完全に忘れ去られた夏季醸造の技術で醸された稀有な日本酒です。
真夏に発酵温度が30度を超える高温条件下で進める醸造法は、江戸時代に日本酒造りが冬季醸造に移行すると姿を消してしまった技術です。
この「水端1355×菩提山正暦寺」は、日本清酒発祥の地 菩提山正暦寺によって育てられた露葉風を、麹造りから実際に正暦寺の大原弘煕副住職にもお手伝いいただきながら、享保蔵にて一緒に醸造した特別な水端です。
正暦寺で栽培される露葉風は、菩提仙川の支流の水を使い栽培されております。
また、元々伽藍があったとされていた場所に田んぼがあり、石垣が組まれていた場所にあるため、水はけが良いのが特徴だそうです。
露葉風は稲がこけやすいため、土用干しを行うことで水を抜き根をはらす作業を行い田植えの間隔を広くすることで稲を太くするなど対策をしているそうです。
色調は、やや濁りのあるシャンパンゴールド。
熟した桃などの果実と、麹由来の甘い栗が複合した重厚な香り。
露葉風の個性であるチリチリとした豊かな複雑味による押し味を感じつつ、切れの良い酸によってスッキリとした後口になっています。
先に発売された「水端1355 2023」に比べると、かなり瑞々しく、全体的にシャープでコンパクトに仕上がっています。
夏季醸造ならではのお酒の味わいと、正暦寺大原副住職と共に造り上げたより深く歴史のエッセンスを含んだ水端をお楽しみいただけます。
また、今回の特別な「水端1355×菩提山正暦寺」の発売を記念して、水端のボトルと同じ、美濃焼で作られた水端オリジナル酒器がセットになっています。
水端をより楽しんでいただけるように、現地の窯と時間をかけて打ち合わせを重ね、試作を繰り返した特別な酒器。
手に取ると、手触りが良く、温かみを感じる質感。
飲み口が広くなっており、濃厚でしっかりとした味わいの水端の魅力をより感じていただけます。
※商品のご購入につきましては、蔵元の意向もあり、お一人さま1商品2本までとさせて頂きます。
※2本以上ご希望の場合は、ご相談ください。
※飲食店さまにつきましては通常通りご購入くださいませ。
|
| 原料米 |
露葉風 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
12度 |
酵母 |
協会7号系 |
|
 |
|
|
|
|
|
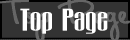 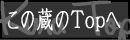 |

油長酒造
水端 1568 2024
|
 |
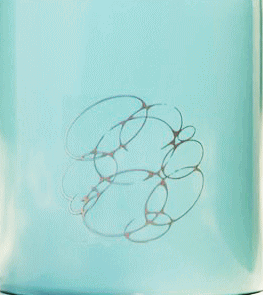 |
甕仕込による古来の製法を再現!
油長酒造の新たな取り組みとなる「水端(みずはな)」は、”忘れられた古の奈良に伝わる技術を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する”をテーマに、古典醸造法を参考にし、大甕で醸造するお酒です。
この「水端 1568」は、「多聞院日記」に記された、興福寺多聞院の技法を参考にした冬季醸造。3段仕込み。
時は室町時代1568年。
奈良の興福寺では寺院醸造の最盛期。
「多聞院日記」という名の寺院の日常を綴った日記が英俊という僧侶によって書か れました。
酒のもろみが搾られて清酒となり、火入れされていることや、奈良酒が本能寺の変の直前の織田信長公へ献上されたという逸話も残っています。
水端1568では「多聞院日記」の1568年の記述を参考に醸造。
大甕で仕込みながらも現代の酒造りに通じる3段仕込みを行い、冬の寒い時期に微生物を巧みにコントロールし、奈良酒の名声を高める高品質な酒造りを行なっていたことが伺えます。
寺院が造り上げた当時最先端の奈良酒は、織田信長公もが愛でたと言われています。
戦国の世に思いを馳せ、水端1568をお楽しみください。
和洋中問わず、現代の食のシーンでも美味しくお召し上がりいただけます。
色調はクリアなシャンパンゴールド。
香りにはナッティーな穀物感。
カラメルのようなニュアンスも感じられます。
口当りには円みがあり、柔らか。
しっとりとした飲み口に甘やかなコク、乳酸系の酸。
リンゴのコンポートや梅酒のようなニュアンスと共に玄米茶やほうじ茶、きな粉のようなニュアンスも感じられます。
リッチな要素に複雑味を感じる複層的な味わい。
個性的ではありつつも、滑らかな飲み心地良さを併せ持ちます。
長期熟成も期待できます。
※商品のご購入につきましては、蔵元の意向もあり、お一人さま1商品2本までとさせて頂きます。
※2本以上ご希望の場合は、ご相談ください。
※飲食店さまにつきましては通常通りご購入くださいませ。
|
| 原料米 |
秋津穂 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
16度 |
酵母 |
協会7号系 |
|
 |
|
|
|
|
|
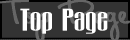 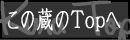 |
|
|
|
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用をお断りします。
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 引用・転載の際は必ずご連絡下さい。
Copyright(C)2005 nobori sake,LTD All Rights Reserved. |
|