|
|
|
菩提もと研究会
菩提泉 2023
|
 |
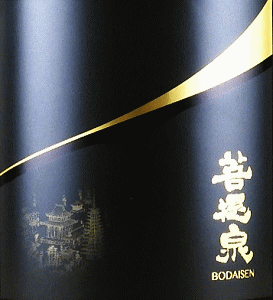 |
日本酒のルーツ”菩提泉”
日本初の民間の醸造技術書『御酒之日記』。
正平10年(1355)もしくは長享元年(1487)に書かれたと言われるこの書物の中に、初めて菩提山正暦寺の酒造りが描かれています。
その酒の名は『菩提泉』。
甕で仕込み、段仕込みを行わない現在の日本酒のご先祖様。
このお酒造りの手法が酒母という形に進化を遂げ「菩提もと」として広く知られていきます。
菩提研ではこの『菩提泉』を正暦寺において2021年復活醸造いたしました。
日本酒の醸造技術の礎ともなった『菩提泉』の復活は、室町時代の寺院醸造の歴史を後世に伝えるための文化的事業と位置付けられます。
日本酒が世界で広く楽しまれるお酒としてご認知をいただく為には、日本酒そのものが持つ味わいの魅力と、そのものが持つ歴史的背景を共に伝えることが必要だと確信します。
原料米は正暦寺によって栽培された奈良県唯一の酒造好適米・露葉風のみを使用。
水は正暦寺に湧く石清水のみを使用しています。
色調は、やや薄めのシャンパンゴールド。
香りは比較的穏やか。
ほのかにプラムのようなのニュアンスがあり、マスカット感も少々感じられます。
口当たりにはプラムやグレープフルーツを思わせる。キリっとした柑橘系の酸を伴うアタック。
砂糖を使用していない梅酒のような印象も感じられます。
意外にクリアな味わいながらも、乳酸感や複雑性があり、インパクトのある酸を甘みが支えるようなイメージ。
非常に個性的でありつつも、興味深い味わいで、菩提もとよりも更に振り切った印象。
このお酒でしか味わえない雰囲気を纏った、何とも不思議な味わいです。
遠い昔の歴史に思いを馳せながらお楽しみください。
【菩提研とは】
平成8年に奈良県内の当時の若手蔵元の有志が集まり、『奈良県 菩提もとによる清酒製造研究会』(菩提研)を設立。 菩提もとの造り方や資料の研究から始まり、菩提山正暦寺と奈良県工業技術センター(現・奈良県産業振興総合センター)とともに菩提もとのお寺での酒造りの再現復活を主導しました。
平成10年(1998)12月11日についに酒母製造免許が下り、寺院醸造を復活。
現在に至るまで20年以上、毎年共同で『菩提もと』を造り続けています。
菩提泉や菩提研についての詳しい情報はこちら
http://bodaimoto.org/
|
| 原料米 |
露葉風 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
14度 |
酵母 |
正暦寺酵母 |
|
 |
|
|
|
|
|
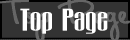 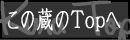 |

菩提もと研究会
菩提泉 2024
|
 |
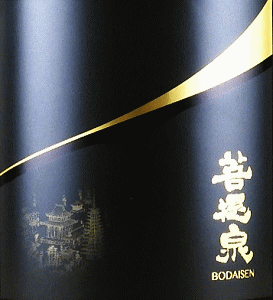 |
日本酒のルーツ”菩提泉”
日本初の民間の醸造技術書『御酒之日記』。
正平10年(1355)もしくは長享元年(1487)に書かれたと言われるこの書物の中に、初めて菩提山正暦寺の酒造りが描かれています。
その酒の名は『菩提泉』。
甕で仕込み、段仕込みを行わない現在の日本酒のご先祖様。
このお酒造りの手法が酒母という形に進化を遂げ「菩提もと」として広く知られていきます。
菩提研ではこの『菩提泉』を正暦寺において2021年復活醸造いたしました。
日本酒の醸造技術の礎ともなった『菩提泉』の復活は、室町時代の寺院醸造の歴史を後世に伝えるための文化的事業と位置付けられます。
日本酒が世界で広く楽しまれるお酒としてご認知をいただく為には、日本酒そのものが持つ味わいの魅力と、そのものが持つ歴史的背景を共に伝えることが必要だと確信します。
原料米は正暦寺によって栽培された奈良県唯一の酒造好適米・露葉風のみを使用。
水は正暦寺に湧く石清水のみを使用しています。
色調は、やや薄めのシャンパンゴールド。
香りは比較的穏やか。
ほのかにヨーグルトやカラメル、穀物感も感じたられます。
口当たりには円みがあり、柔らか。
軽やかで、しっとりとした飲み口に、ややクリアさを感じるスマートな旨み。
しっかりとした乳酸系の酸、菩提泉らしいワイルドな要素や複雑性はありつつも、グレープフルーツのような果実感を感じるジューシーな甘酸っぱさがあり、意外と軽快でクリーンな味わいです。
非常に個性的でありつつも、興味深い味わいで、菩提もとよりも更に振り切った印象。
このお酒でしか味わえない雰囲気を纏った、何とも不思議な味わいです。
遠い昔の歴史に思いを馳せながらお楽しみください。
【菩提研とは】
平成8年に奈良県内の当時の若手蔵元の有志が集まり、『奈良県 菩提もとによる清酒製造研究会』(菩提研)を設立。 菩提もとの造り方や資料の研究から始まり、菩提山正暦寺と奈良県工業技術センター(現・奈良県産業振興総合センター)とともに菩提もとのお寺での酒造りの再現復活を主導しました。
平成10年(1998)12月11日についに酒母製造免許が下り、寺院醸造を復活。
現在に至るまで20年以上、毎年共同で『菩提もと』を造り続けています。
菩提泉や菩提研についての詳しい情報はこちら
http://bodaimoto.org/
|
| 原料米 |
露葉風 |
精米歩合 |
非公開 |
| 日本酒度 |
非公開 |
酸度 |
非公開 |
| アルコール度 |
13度 |
酵母 |
正暦寺酵母 |
|
 |
|
|
|
|
|
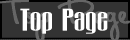 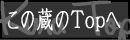 |
|
|
|
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用をお断りします。
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 引用・転載の際は必ずご連絡下さい。
Copyright(C)2005 nobori sake,LTD All Rights Reserved. |
|